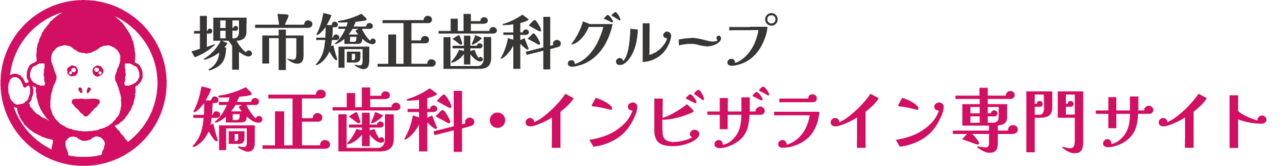堺市で矯正歯科・インビザラインなら
なかもずますだ歯科・矯正歯科 / 〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町5丁764−2 中百舌鳥ビル 1階 /大阪メトロ御堂筋線「なかもず駅」より徒歩5分
きたはなだますだ歯科・矯正歯科 / 〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町 2-4-1コプリー1階 /大阪メトロ御堂筋線「北花田駅」より徒歩1分
しんかな歯科・矯正歯科 / 〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町 3069-9 カルム新金岡B.L.D1階/大阪メトロ御堂筋線「新金岡」より徒歩1分
鳳よしむら歯科・矯正歯科 / 〒593-8325 大阪府堺市西区鳳南町 1-1-1東勝ビル1階/JR阪和線「鳳」駅より徒歩3分
堺で有数の矯正歯科グループ
よくあるご質問
患者さまからよくいただくご質問をまとめました。
基本的に大なり小なり痛みは伴いますし、口内炎ができたりすることもございます。これらのリスクに対し私どもでは痛み止めや口内炎のお薬、うがい薬などを、矯正治療開始時に「矯正スターターパック」としてお渡しいたしますので、安心して治療を受けていただけるのではないでしょうか。
また当グループでおススメしているマウスピース矯正「インビザライン」の場合は、ワイヤーを使った一般的な矯正と比べ、痛みが少ないと言われています。
痛みを少なくするためには、定期的に歯科検診とクリーニングを受けていただき、常にお口の中を口内炎のできにくい清潔な環境に保つことが肝心です。私どもでは矯正治療中、3か月に1回歯科検診とクリーニングを行いますので、安心して受診していただければと思います。
基本的に大なり小なり痛みは伴いますし、口内炎ができたりすることもございます。これらのリスクに対し私どもでは痛み止めや口内炎のお薬、うがい薬などを、矯正治療開始時に「矯正スターターパック」としてお渡しいたしますので、安心して治療を受けていただけるのではないでしょうか。
また当グループでおススメしているマウスピース矯正「インビザライン」の場合は、ワイヤーを使った一般的な矯正と比べ、痛みが少ないと言われています。
痛みを少なくするためには、定期的に歯科検診とクリーニングを受けていただき、常にお口の中を口内炎のできにくい清潔な環境に保つことが肝心です。私どもでは矯正治療中、3か月に1回歯科検診とクリーニングを行いますので、安心して受診していただければと思います。
たくさんのリスクが考えられます
歯並びの乱れは、いろいろな問題に波及することがあります。最もわかりやすいのは“口元のコンプレックス”ですね。小さい頃は気にならなくても、成長するにつれ、出っ歯や乱ぐい歯といった悪い歯並びがコンプレックスになるというケースは珍しくありません。悪い歯並びを見られたくないという気持ちから、自然に笑えなくなる人もいらっしゃいます。
次に、歯並びの乱れを放置することによる“そしゃく機能の低下”が挙げられます。歯並びに乱れがあるというのは、単に見た目が悪いだけでなく、かみ合わせにも異常が生じている状態です。上下の歯列で上手くかみ合うことができず、そしゃくする機能が低下します。その結果、食べられるものに制限がかかったり、歯や顎の骨に過剰な負担がかかったりします。
利点は歯並び・かみ合わせが正常になること、欠点はお金と時間が必要になることです
矯正治療には、たくさんの利点がありますが、同時にいくつかの欠点も存在しています。利点としては、歯並びが正常になり、見た目が美しくなることが挙げられます。矯正治療を希望する多くの人は、この点に着目しています。実はそれ以外にも機能面や健康面において非常に重要な利点が存在しています。
歯並びが良くなると、かみ合わせも正常化され、効率良く噛めるようになりますよね。つまり、そしゃく能率が向上して、いろいろな性状の食べ物をストレスなく噛めるようになります。歯や顎にかかる負担も減り、口腔周囲の健康維持・増進にもつながります。
また、歯並びが整うことで清掃性が高まり、歯垢や歯石、食べかすなどが溜まりにくくなります。その結果、むし歯や歯周病のリスクが低下します。口臭も発生しにくくなるという利点もあります。
次に矯正治療の欠点ですが、これは比較的長い治療期間が第一に挙げられます。一般的な矯正治療は、1~3年の期間を要します。その間、矯正装置を装着しなければならないので、心身への負担もそれなりに大きくなります。また、保険が適用されないことから、治療にかかる費用が高額になる傾向にあります。これらが矯正治療に伴う欠点です。利点と欠点の両方を踏まえた上で、矯正治療を受けるかどうか、検討することが大切です。
歯科医師ごとに技術や知識に大きな差があります
歯科医師の技術や知識は、それぞれで大きく異なります。ましてや専門性の高い矯正治療となると、その差はさらに広がります。ですから、矯正の先生によって上手・下手は確実にあるといえます。歯列矯正は数年に及ぶものであり、一生に一度、受けるか受け内科の治療であることから、できるだけ上手な先生にお願いしたいものですよね。
そこでまず上手な先生を見つけるポイントして、認定医などの資格の有無に着目してみましょう。矯正治療は歯科医師であれば誰でも行うことができますが、認定医や指導医の資格を持っている人と、そうでない人との差は極めて大きいです。
また、 上手な人は、たくさんの成功例を持っていることかと思いますので、カウンセリングの際に過去の症例の説明を求めましょう。とくに自分と同じ歯並びの症例で、どのような治療を施し、どのような結果が得られたのか質問すると良いです。
もちろん、矯正医の資格を持っていなくても治療が上手な先生はいますので、あくまで参考程度にとらえてください。
当院は矯正治療の経験が豊富でインビザラインの認定医であるため、安心してご相談ください。
お一人おひとりで異なります
矯正治療を受ける最適な時期というのは、患者さまお一人おひとりで異なります。とくに小児矯正に関しては、ケースによってバラつきが大きいといえるでしょう。例えば、受け口の症状が認められたら、比較的早期に治療を開始した方が良いといえます。受け口あるいは下顎前突の症状が気になった時点で一度、矯正歯科を受診しましょう。
小児矯正は、混合歯列期から開始するのが一般的です。乳歯列が完成するのは3歳くらいですが、その時点で矯正治療を開始しても、あまり高い効果は得られません。大人の歯が生え始める6歳くらいが適切です。
小児矯正における第二期治療は、顎の骨の発育が完了してから開始します。目安となる時期は、中学生から高校生にかけてです。細かい歯並びの調整を行っていきます。これはいわゆる「歯列矯正」であり、マルチブラケットやマウスピースを用いて矯正します。成人矯正とも呼ばれる治療法であり、顎の発育が完了していれば、原則として何歳になっても受けることが可能です。
ただ、余裕があるのなら、成人矯正も早い時期に受けた方がメリットも大きくなります。歯並びの乱れは、審美性を低下させるだけでなく、むし歯や歯周病のリスクを上昇させるからです。また、かみ合わせも乱れることで、歯や顎にかかる負担が多くなることから、早期に改善した方が患者さまにとって有益といえます。
成人矯正は何歳になっても受けることができます
矯正治療の悩みで、意外に多いのが年齢に関する不安です。矯正治療は子どもの頃に受けるもの、というイメージが強いためか、年齢が高くなると治療そのものが受けられなくなると誤解されている方も少なくありません。
結論からいうと、成人矯正は何歳になってからでも受けることができます。実際、40歳や50歳から歯列矯正を始める人はたくさんいらっしゃいます。ですから、矯正治療というのは思い立った時に、いつでも始められますが、お口の中の状態によっては難しくなることもあります。その点は、カウンセリングや検査を行わなければわかりません。
また、年齢が高くなるにつれて、歯の本数が減ったり、顎の骨の状態が悪くなったりするなど、矯正治療において不利な要素が増える傾向は否めません。そのため、成人矯正を検討中の方は、まず歯医者さんに相談することをおすすめします。何歳になっても受けられる治療とはいえ、早いに越したことはありません。カウンセリングを受けたからいって、必ず治療を始めなければならないというわけではないので、まずは気軽に相談してみましょう。
小児矯正に関しては受けられる年齢がある程度決まっているため、年齢が高くなった後は選択肢として除外されます。歯や顎の発育が途上にある段階で始めるようにしましょう。
基本的にはありません。
ブラケットと矯正用ワイヤーを用いたマルチブラケット法では、装置による違和感や異物感が大きくなります。そのせいで楽器が演奏しにくくなったり、スポーツのパフォーマンスが低下したりすることはあるかもしれませんが、それらを控えなければいけなくなることはありません。矯正治療前と同じように、楽器の演奏やスポーツを継続していただいて問題ありません。
ただ、楽器の種類によっては、矯正装置が邪魔で演奏できなくなるケースもあり得ます。また、空手やボクシングのようなフルコンタクトの格闘技では、矯正装置による口腔粘膜の裂傷などが想定されます。いずれも症状を緩和する方法はありますが、リスクをゼロにすることは難しいため、矯正前にしっかりと把握しておくことが大切です。
マウスピース型矯正装置のように、異物感や違和感が小さく、口腔粘膜を損傷する恐れが低い矯正法もありますので、不安な方は選択肢の一つとして考えてみましょう。大切なのは、患者さまが何を優先するかです。今行っている楽器の演奏やスポーツが最も優先されるのであれば、それに見合った矯正法を選択するか、治療の開始時期を再度検討するのも良いかと思います。
とはいえ、一般的な症例では、矯正を始める前と同じように楽器やスポーツを続けられますのでご安心ください。
保定期間は3~6ヶ月に1回くらいの頻度で通院していただきます
矯正治療後の保定は、歯の後戻りを防止するために行う処置です。リテーナーと呼ばれる専用の装置を装着して、歯の位置を固定します。歯を矯正力によって移動させる動的治療とは異なり、あくまで歯並びを安定させることが目的なので、それほど頻繁に通院する必要はありません。一般的には3~6ヶ月に1回くらいの頻度で十分です。
保定期間に入って間もない頃は、3ヶ月に1回のくらいの通院頻度が適切といえます。矯正が終わったばかりなので、最も後戻りしやすい時期だからです。その後は徐々に通院する間隔を開けていくこととなります。最終的には6ヶ月に1回程度の通院で十分となります。
とはいえ、矯正が終わったのになぜ引き続き通院しなければならないのか、不思議に思う方もいらっしゃることでしょう。矯正治療というのは、矯正装置を用いて、半ば強引に歯を移動させる処置です。そのため、矯正装置を外してしまえば、歯が元の位置に戻ろうとするのも自然の減少といえます。
ただ、適切な保定処置を施すことによって、顎の骨や歯周靭帯も移動後の歯に見合ったものに変化していきます。その結果、矯正治療によって整えられた美しい歯並びが自然な状態となるのです。そういう意味で保定期間は、歯を動かす期間と同じくらい重要なものであるといえます。
矯正治療は期間に余裕を持って開始した方が良いです
一般的な矯正治療は、1~3年程度の期間を要します。その間に、転院が予想される場合は、転居後に矯正治療を開始した方が良いといえます。矯正治療というのは、スタートからゴールまでを決めた上で開始するものなので、途中で施術を担当する歯科医師の変更は、あまり良い結果を生みません。
それでもなお短期間で治療を終えたいのであれば、「部分矯正」という選択肢が推奨されます。その名の通り“前歯だけ”など歯列の一部分を矯正する治療で、ケースによっては半年程度で完了します。ただし、適応できる症例は限られますし、歯並び全体を整えることができないので、かみ合わせが悪くなることも珍しくありません。
転院を前提に全顎矯正を希望される場合は、矯正システムが確立されたマウスピース型矯正装置を選択するのもひとつの方法といえます。それでも患者さまにとってデメリットとなる点は少なくないため、基本的には推奨されません。
成人矯正は、開始するのが数ヶ月から1年程度遅れたとしても、治療の効果にそれほど大きな違いはありませんので、焦って開始する方がデメリットも大きいです。数ヶ月から1年程度先に遠くへの転勤が予定されているのであれば、転居後に再度検討する方が望ましいです。その点も踏まえ、一度矯正歯科に相談してみましょう。
矯正治療は期間に余裕を持って開始した方が良いです
一般的な矯正治療は、1~3年程度の期間を要します。その間に、転院が予想される場合は、転居後に矯正治療を開始した方が良いといえます。矯正治療というのは、スタートからゴールまでを決めた上で開始するものなので、途中で施術を担当する歯科医師の変更は、あまり良い結果を生みません。
それでもなお短期間で治療を終えたいのであれば、「部分矯正」という選択肢が推奨されます。その名の通り“前歯だけ”など歯列の一部分を矯正する治療で、ケースによっては半年程度で完了します。ただし、適応できる症例は限られますし、歯並び全体を整えることができないので、かみ合わせが悪くなることも珍しくありません。
転院を前提に全顎矯正を希望される場合は、矯正システムが確立されたマウスピース型矯正装置を選択するのもひとつの方法といえます。それでも患者さまにとってデメリットとなる点は少なくないため、基本的には推奨されません。
成人矯正は、開始するのが数ヶ月から1年程度遅れたとしても、治療の効果にそれほど大きな違いはありませんので、焦って開始する方がデメリットも大きいです。数ヶ月から1年程度先に遠くへの転勤が予定されているのであれば、転居後に再度検討する方が望ましいです。その点も踏まえ、一度矯正歯科に相談してみましょう。
技術や知識、診療実績に大きな違いがあります
矯正歯科の認定医や指導医は、どちらも専門医制度の資格の一種ですが、優劣をつけるとなると、明らかに指導の方が優れているといえます。なぜなら、認定医を育てるのが指導の役割だからです。その分、矯正歯科に関する技術や知識、診療実績なども指導医の方が圧倒的に豊富です。
具体的には、まず矯正の診療実績の経験年数が異なります。認定医になるためには、少なくとも5年以上の矯正治療の実績が必要ですが、指導医ともなると12年以上は必要となります。この時点で、認定医と指導医にどれだけの違いがあるか、理解できることかと思います。
当然、指導医は認定医の資格をもっているのですが、さらに大学病院での教育歴が3年間必要となります。それだけに、全国でも矯正歯科の指導医の資格を持っている歯医者さんはほんの一握りといえるでしょう。
ですから、矯正の歯医者さんを探す際には、認定医の資格を有しているだけでも信頼性は高まります。日本矯正歯科学会によって、一定水準以上の知識や技術が保証されているからです。その上、指導医の資格まで持っているとなれば、安心して治療を任せることができますね。
ただし、認定医や指導の資格の有無がすべてではありません。そうした資格を持っていなくても素晴らしい技術を備えた歯医者さんがいますので、あくまで参考程度にお考えください。
一部のケースでは保険で矯正治療が受けられます
矯正治療は原則として自由診療となりますが、一部例外的に健康保険で受けられるケースがあります。それは歯や顎に先天的な異常がある場合です。
例えば、唇顎口蓋裂やダウン症候群、トリーチャー・コリンズ症候群などは、生まれながらにしてお口の中にさまざまな異常が認められます。その中には歯並びに関する症状もあるため、例外的矯正治療を保険で受けることが可能です。ちなみに厚生労働省は、約60の先天異常を矯正治療の対象として挙げています。
その他、顎の骨の大きさや位置、形の異常によって顎変形症を発症している場合や、歯の先天欠如による咬合異常なども、ケースによっては保険で矯正できます。
とはいえ、上記のケースはあくまで例外であり、原則として矯正は自由診療で受けることとなります。なぜなら、大半のケースは審美性の向上を目的としているからです。歯科に限らず、医科の治療も美容目的であれば、保険は適用されませんよね。やはり、歯並びをきれいに整えるというのは、むし歯や歯周病を治療するのとは少し異なる性質があるといえるのです。
もちろん、一般的な矯正治療も審美性の向上だけでなく、機能性の改善も併せて行うため、単に見た目を美しくするだけの治療は存在しません。当院の矯正も審美性と機能性の両方を向上させる治療に努めております。
1年間で支払った医療費の金額が10万円を超える場合、医療費控除を申請することができます。10万円というと、かなり高額に思えますが、矯正治療であれば、ほぼすべてのケースに当てはまるといえます。ただ、矯正治療は審美性の向上を目的とすることが多く、そもそも医療費控除の対象にはならないと思っている方も少なくありません。
確かに、審美性を向上させるためだけの矯正治療は、医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。矯正治療によって見た目が美しくなるだけでなく、かみ合わせなどの異常もしっかり改善できなければ医療費控除は認められません。ですから、まずは矯正歯科で治療が必要であるかを診断してもらう必要があります。
その上で、歯科医師が審美性のみならず機能性の改善においても矯正治療が必要と判断されたケースに限り、医療費控除の対象となります。とはいえ、歯並びに異常があるということは、同時にかみ合わせにも異常が生じているため、実際は多くのケースで医療費控除の対象となります。
矯正治療は比較的高額な費用がかかるだけに、できるだけ出費を抑えたいものですよね。ですから、矯正治療を検討中の方は、医療費控除も視野に入れておきましょう。矯正治療における医療費控除についてさらに詳しく知りたい場合は、お気軽に当院までご相談ください。
精密な診断を下すためにさまざまな検査を実施するからです
むし歯や歯周病のような一般歯科の治療では、検査の費用に数万円もかかることはありません。口腔内診査やレントゲン撮影を行うだけで、病気の状態を把握できるからです。一方、矯正治療ともなると、話は変わります。
口腔内診査やレントゲン撮影は当然行うのですが、「セファログラム」という特別な画像診断も実施する必要があるのです。これは歯の周囲だけでなく、顔面や頭部の骨格まで含まで含めた広範囲なレントゲン撮影を行うものです。また、特別な模型を作ったりするなど、一般歯科の治療とは異なる部分が多々あります。そのため、矯正治療では検査料も比較的たかくなってしまうのです。
ちなみにセファログラムを撮影できる機器というのは、どの歯科医院にも設置されているわけではありません。基本的には矯正治療を専門に行っている歯科医院しか導入しておらず、設備費用もかなり高額となっています。また、矯正治療の検査が保険適用されないという点も料金が高くなる一因といえるでしょう。
このように、矯正治療では特別な精密検査を行うため、検査料が数万円かかることも珍しくありません。ただ、いずれの検査も適切な診断を下す上で必須となっており、省略することは難しいです。そうした背景も含めて、矯正治療を検討することが大切です。
顔貌写真の撮影は治療に必要ですがプライバシーは保護されます
矯正治療を希望してカウンセリングを受ける際には、その医院が過去に治療した症例の説明が入ることもあります。その際、患者さまの顔が写り込んだ写真も含まれていることがありますが、そうした画像を提供していただく場合、必ずご本人の了承を得ています。患者さまの同意を得ないまま、顔貌写真等を公表することは絶対にありませんのでご安心ください。
次に、矯正治療で顔写真を撮る理由についてですが、これは診断を下す際や治療計画を立案する段階で必要となるからです。歯列の状態を正確に診断するためには、歯の情報だけでなく、顔や骨格の形態なども精密に分析する必要があります。ですから、普段の歯科治療とは異なる種類の写真を撮ることも多くなりますが、それは矯正治療を進めていく上で欠かすことのできないものであるということをご理解ください。治療の経過を見る際にも、大いに役立つ資料となります。
矯正のレントゲン撮影によって健康被害が生じるリスクは極めて小さいです
治療や検査に伴うリスクをゼロにすることは不可能です。それは矯正治療におけるレントゲン撮影も同じです。ただし、もともと健康な方が矯正のレントゲン撮影によって体調を崩したり、副作用が生じたりするリスクは極めて小さいです。矯正のレントゲン撮影に伴う被ばく量も微々たるものなので、ご安心ください。
ちなみに、歯科で行うレントゲン撮影というのは、基本的に首から上しか放射線が当たりません。一般的なデンタルやパノラマは、放射線の照射範囲が口腔周囲に限定されることから、被ばく量はさらに少なくなります。矯正のセファログラムは、頭部も含まれており、比較的照射範囲が広くはなりますが、医科のレントゲンと比べるとかなり限定的です。
また、歯科のレントゲン撮影では、必ず鉛製のエプロンを装着することから、首より下の臓器の防護も万全となっています。そういう意味でも、矯正治療で行うレントゲン撮影は、健康を害するリスクの少ないものといえます。
もちろん、患者さまのお身体の状態や持病の種類などによっては、レントゲン撮影を控えた方が良いこともあります。ですから、カウンセリングの段階で、今現在服用しているお薬の種類や治療中の病気などは、できる限り正確に申告するようにしましょう。
転居先から引き続き通院するのが最善といえます
矯正中に引っ越しが決まった場合、選択肢は2つとなります。1つ目は、矯正を開始した歯科医院に継続して通院することです。歯列矯正というのは、始めから終わりまで、一人の矯正医に任せるのが一番です。途中で転院してしまうと、治療計画そのものを大きく変えるか、作り直さなければならなくなります。それは患者さまにとって極めて大きなデメリットとなります。
2つ目の選択肢は、転居先で新たに矯正歯科を探して、転院することです。転居後のお住まいから、現在通っている歯科医院への通院が困難な場合は、この選択肢を選ぶこととなります。その際、主治医からは紹介状を書いてもらった上で、治療に関する一連の資料の提供も受けましょう。それらがそろっていれば、次の矯正歯科への転院もスムーズに進みます。
ただし、矯正治療における転院は、患者さまのデメリットが非常に多くなります。治療費が余計にかかることはもちろん、矯正にかかる期間も長くなるのが一般的です。ですから、転勤によって引っ越す場合でも、引き続きかかりつけ医に通院する方法をまずは模索しましょう。それでも難しい場合に転院を選ぶことをおすすめします。
このように、矯正中の引っ越しは誰にでも起こり得ることですが、注意しなければならない点が多々あります。転居前に必ず主治医と相談した上で、最善といえる方法を選びましょう。
一般的な歯列矯正は1~3年ほどかかります
矯正治療にはたくさんの種類があり、治療にかかる期間もさまざまです。そこでまず最もポピュラーな「歯列矯正」を例に挙げると、矯正にかかる期間は1~3年程度です。これはマルチブラケットやマウスピースを用いた矯正法で、歯を動かすのに必要となる期間です。歯の移動が完了したら、後戻りを防止する「保定期間」へと入ります。リテーナーと呼ばれる装置を用いて、動かした歯の固定を行う期間。
一般的に保定は、歯の移動と同じくらいの期間が必要となることから、すべて合わせると2~6年の期間を要するといえます。ただ、保定装置は着脱式のものが多く、あくまで歯列の固定を行うものなので、心身にかかる負担は比較的小さいです。そのため、マルチブラケットなどによって歯を動かしている時のような苦労がその後も1~3年続くというわけではないのでご安心ください。
いわゆる「部分矯正」であれば、6ヶ月程度で治療が完了します。治療期間をできるだけ短くしたい、歯列の気になっている部分だけ治したい、という方にはおすすめの矯正法といえます。子どもが受ける「小児矯正」の治療期間はケースバイケースです。気になる方はまず歯医者さんに相談してみましょう。
このように、矯正は長期間に及ぶ歯科治療なので、その点を踏まえた上でしっかり検討する必要があります。
矯正に伴う痛みは個人差が大きいです
歯列矯正は、矯正装置によって歯を人為的に動かす処置なので、少なからず不快感や痛みを伴います。その程度は、人によってさまざまです。ほとんど気にならないという方もいらっしゃれば、痛みに慣れるまでに時間がかかった、とおっしゃる方もいます。いずれのケースにも言えるのは“我慢できないほどの痛み”ではないという点です。
矯正治療を始めた当初は、少し強い痛みが生じるかもしれません。ほとんどの人は、人為的に歯を動かす、という経験が初めてですし、最初は最も強い矯正力が働きやすいからです。それが徐々に慣れてくると、気にならなくなる人が大半を占めます。そこで我慢できないほどの痛みを感じるのであれば、矯正装置に何らかの問題があるのかもしれません。かかりつけ医を受診して、ワイヤーやマルチブラケットを調整してもらいましょう。
ちなみに、歯列矯正に伴う痛みというのは、ケガをした時の痛みではなく、“歯が引っ張られるような感覚”といった方が正確かもしれません。ですから、強い痛みではなく、不快感のようなものなので、それほど心配する必要はありませんよ。痛みや不快感が苦手な場合は、それも主治医に事前に伝えておきましょう。ブラケットやワイヤーを設置する際に、そうした点も考慮してくれることかと思います。その他にも、矯正中の痛みや不快感を軽減する方法はいくつかあります。
適切なケアを実施しましょう
矯正中は、むし歯や歯周病のリスクが高まります。とくに装置が複雑なワイヤー矯正は、清掃性が悪く、食べ物が詰まりやすいため要注意です。そのまま放置すると細菌が繁殖し、むし歯や歯周病になってしまいます。
矯正歯科では、治療を始める前に必ず口腔清掃に関する指導が入るかと思います。普段の口腔ケアでは、その指導に従ってブラッシング等を行いましょう。それでもなお矯正装置に食べ物が詰まったり、プラークが堆積したりする場合は、再度をブラッシング指導を受ける必要があります。
矯正中の歯磨きは、いろいろな工夫が必要となるため、慣れるまでに時間がかかります。それでも頑張ってプラークフリーな状態を確立できるよう努めましょう。適切なブラッシング法は、矯正の通院の度に教えてもらうのも良いです。同時に、歯科衛生士によるプロフェッショナルケアも受けることをおすすめします。
矯正歯科では、さまざまな器具を使って、矯正装置のお掃除も行っています。そうしたプロフェッショナルケアとセルフケアを両立して初めて良好な口内環境を維持することが可能となります。ちなみに、矯正中にむし歯になってしまうと、治療計画が大きく乱れることとなるため要注意です。矯正を始める前以上に、むし歯の予防に努めましょう。歯並びがきれいになっても、むし歯で歯がボロボロになってしまったら元も子もありません。
しんかな歯科
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × |
午前:9:30~13:00
午後:14:30~19:30
△ 9:00~13:00/14:00~18:00
休診日:火曜・日曜・祝日
アクセス
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町3069-9
大阪メトロ御堂筋線「新金岡駅」徒歩3分
きたはなだますだ歯科
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | × |
| 午後 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◇ | × |
午前:9:30~12:30
午後:14:30~19:00
△ :水曜日14:00~17:00
◇ :土曜日9:00~12:30
14:00~18:00
休診日:日曜・祝日
アクセス
〒591-8002
大阪府堺市北区北花田町2-4-1
大阪メトロ御堂筋線「北花田駅」徒歩1分